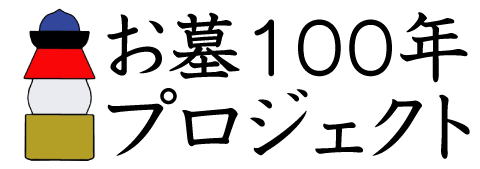奨励賞

母の墓参
一日のほとんどを家の中で過ごすようになった89歳の母が、故郷へ墓参りに行きたいとしきりに言うようになった。
8人兄弟姉妹のうち母一人となっていた。
夫が行こうと言ってくれたので、秋のある日、母は車で2時間ほどの山間にある生家へ何年振りかで帰った。
私も妹たちと小学生の夏休みや冬休みには、何日間か過ごした懐かしいところだ。
川遊びや、伯母の手ほどきで芽茶を作ったりもした。
従兄の運転で、母より5歳年上の兄嫁である伯母と5人で墓地へ行った。
途中からは人が一人歩ける程の細い登り道となる。夫が母を背負った。
寒がりの母は冬衣装で、小柄とはいえ背負いにくかったことだろう。
夫は万一転んでも、自分が下敷きになるようにと考えていたと、後で話した。
両親と戦死した長兄と弟が眠る墓は、家の方を向いて並んで建ち、晩秋の午後の光を浴びていた。
私もその光を浴びながら、死者を介してのつながりや来し方の人生を思った。
伯母に世話になった恩、夫が母を背負ってくれるありがたさをである。
「クニエが来ました」と言ったという。
わたしは写真を撮ろうと後ろの方にいたので聞こえなかった。夫が聞いていた。
土葬の母にわが名を告げて、母は共に暮らしていた昔日の時間の中にいたことだろう。
この写真は苔むした墓の前に佇む、母と夫の姿である。
私たちはしばしばその墓地の温もった山肌にいた。
母は伯母と並んで傍らの石に腰をおろし何ごとかを語らい、私たちは山なみを眺めた。
遠くに黄葉したイチョウが夕日に染まっていた。
それから2年の後、今から6年前の大晦日に、母はこの世を去った。